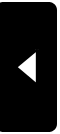利益が出ている企業は「当座資産と内部留保を高めている」
2010年09月21日
自分自身が初心を思い出すためのメモ書き
今回は、「利益が出ている企業は「当座資産と内部留保を高めている」」ことについてお話をしようと思います。
( わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください
わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください )
)
 利益が出ている企業がしていること、または、しなければならないことの一つに、長引く不況などに備え「当座資産と内部留保を高める」ことがあります。
利益が出ている企業がしていること、または、しなければならないことの一つに、長引く不況などに備え「当座資産と内部留保を高める」ことがあります。
 企業は、利益を出す(利益を追求する)必要がありますが、いつも業績が良いとは限りません
企業は、利益を出す(利益を追求する)必要がありますが、いつも業績が良いとは限りません
長引く不況やライバル店の出現などにより、売上げが半分にまで減収となる可能性もあります
そうなれば、今まで通りの経費を使っていれば、利益を出すことは難しくなるどころか、資金繰りも悪化します
 こういった場合、「当座資産(現金など)」や「内部留保」がない企業は、外部から資金調達できなければ、企業の存続が危うい状態となります
こういった場合、「当座資産(現金など)」や「内部留保」がない企業は、外部から資金調達できなければ、企業の存続が危うい状態となります
 一方、「当座資産」や「内部留保」を充分に蓄えている企業は、少しずつ取り崩しながら、景気が回復するのを待ったり、新しい商品やサービスの開発をすることができるので、少しでも長く企業を存続することができます
一方、「当座資産」や「内部留保」を充分に蓄えている企業は、少しずつ取り崩しながら、景気が回復するのを待ったり、新しい商品やサービスの開発をすることができるので、少しでも長く企業を存続することができます
 注意したいのが、「当座資産」が充分にあっても、「流動負債」が同額、または、当座資産以上にある場合は、資金ショートを起こす可能性があり、企業を存続することができない場合があります(流動比率が100%以下の企業など)
注意したいのが、「当座資産」が充分にあっても、「流動負債」が同額、または、当座資産以上にある場合は、資金ショートを起こす可能性があり、企業を存続することができない場合があります(流動比率が100%以下の企業など)
 【内部留保を高める方法】
【内部留保を高める方法】
 1.利益を出すこと
1.利益を出すこと
利益が出ない限り、内部留保することはできません。
 2.配当金や役員賞与を少なくする
2.配当金や役員賞与を少なくする
配当金や役員賞与は利益の中から支払いすることになりますので、その分内部留保は少なくなります
最近は外国人投資家の比率が高まっているなどの理由により、「株主の利益を重要視して」最終損益が赤字となっていても、「内部留保(利益剰余金)」を取り崩してでも配当するといった企業が増加傾向にあり、賛否両論です
配当金や役員賞与は現金で出ていきますから、当座資産を高めるという見方をすれば、少ないほうが良いです
 3.節税をする
3.節税をする
「試験研究費を使った」「教育訓練費を使った」「中小企業が新品の機械や備品や車両を購入した」場合などは、一定の条件はありますが、「法人税を減額する」「圧縮記帳」などといった選択肢もありますので、「社員教育や設備投資の充実を図りながら、税金を少なくし、内部留保を高めること」ができます。
しかし、「法人税が減額となる」からといって、企業にとって不要なものを購入しては、本末転倒です。
 【当座資産を高める方法】
【当座資産を高める方法】
 1.配当金や役員賞与を少なくする
1.配当金や役員賞与を少なくする
上記の【内部留保を高める方法】を参考にしてください
 2.税金を払う
2.税金を払う
税金を払うのはもったいないという認識をしていませんか?
確かに税金の使途によっては、払うのはもったいないかもしれません。
しかし、利益に対して、税金を払うことによって、現金は残ります。(利益で設備投資、借入金の返済をしなかった場合)
損金にできる積立型の生命保険に加入するといった手段などはありますが、税金を払うのが嫌だからといって、企業にとって不要なものを購入すれば、いずれにしても「現金」が出ていきますからお金は残りません
 翌期に「購入」「修理」などを検討しているものであれば、前倒しして経費にするのであればいいと思いますが、100万円の利益がでて税金を払うのが嫌で、100万円分の不必要な経費を使ったとすれば、最終的に現金は残りませんので再度検討すべきです
翌期に「購入」「修理」などを検討しているものであれば、前倒しして経費にするのであればいいと思いますが、100万円の利益がでて税金を払うのが嫌で、100万円分の不必要な経費を使ったとすれば、最終的に現金は残りませんので再度検討すべきです
 また、100万円分の不必要な経費を使うのであれば、利息の付く借入金(有利子負債)を早期に返済し、金利分を節約する方が資金の使い方としては有意義となる場合があります
また、100万円分の不必要な経費を使うのであれば、利息の付く借入金(有利子負債)を早期に返済し、金利分を節約する方が資金の使い方としては有意義となる場合があります
 例えば、100万円の利益で法定実効税率(利益に対する税負担率)が40.87%とすれば「現金が591,300円」残ります
例えば、100万円の利益で法定実効税率(利益に対する税負担率)が40.87%とすれば「現金が591,300円」残ります
********************
法人税など=100万円×40.87%=408,700円
現金・預金=100万円-408,700円=591,300円
*上記の算出式は利益が出ていないときの実効税率で、【法人税率:30%、事業税率:9.6%、住民税率:17.3%】で計算しています。
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引き下げられていますのでお気をつけください。
********************
↓わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください↓
 香川県を活性化させよう
香川県を活性化させよう
サークルへの参加も宜しくお願い致します。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1958
 ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。
ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。
職業に関係なく、是非、ご参加ください。
香川県を盛り上げていきましょう!
香川に縁のある方であれば、誰でも参加OKです。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1959
 顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
お問合せは、プロフィールのホームページから
 また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪
また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪
お気軽にお問合せ下さい
以下、用語の簡単な説明です。
********************
 【当座資産】
【当座資産】
「現金・預金」「受取手形」「売掛金」「(一時所有の)有価証券」などで、短期間のうち(1年以内)に現金化できる資産のことをいいます。
 【流動負債】
【流動負債】
1年以内に支払の期限が到来する債務のことをいいます。
 【流動比率】
【流動比率】
「計算式=流動比率(%)=流動資産÷流動負債」で、企業の1年以内の収支倍率(支払能力)を表す数値で、100%以上であれば、1年以内に支払不能になる可能性が低いことを表します。
この数値が低すぎる場合、企業の健全性に問題が生じている可能性がありますが、逆に高すぎる場合も、遊休資産が多いとみなされ、買収の対象になる可能性が高くなります。
 【内部留保】
【内部留保】
企業が活動して獲得した利益のうち、「法人税などの税金」「役員賞与」「剰余金による配当」を払った残りで、企業内部へ再投資する目的で蓄積されている部分(利益剰余金)です。
要は、企業の設立から現在までの「利益の累積額」です。
 【法定実効税率】
【法定実効税率】
理論上の利益に対する税負担率です。
法人の所得には、条件にもよりますが、基本的には【法人税(国税)30%】【法人住民税(地方税)9.6%】【法人事業税(地方税)17.3%】の税金が課されます。
この3つの税率を単純に加算すると、44.79%となります。
しかし、事業税は支払いをする日を含む事業年度において損金算入(経費)とされるため、結果として節税効果が生じます。
このことを考慮して算出した理論上の利益に対する税負担率を「実効税率」といいます。
算出式は、以下のとおり。
「実効税率=法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率/1+事業税率」
********************

今回は、「利益が出ている企業は「当座資産と内部留保を高めている」」ことについてお話をしようと思います。
(
 わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください
わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください )
) 利益が出ている企業がしていること、または、しなければならないことの一つに、長引く不況などに備え「当座資産と内部留保を高める」ことがあります。
利益が出ている企業がしていること、または、しなければならないことの一つに、長引く不況などに備え「当座資産と内部留保を高める」ことがあります。 企業は、利益を出す(利益を追求する)必要がありますが、いつも業績が良いとは限りません
企業は、利益を出す(利益を追求する)必要がありますが、いつも業績が良いとは限りません
長引く不況やライバル店の出現などにより、売上げが半分にまで減収となる可能性もあります

そうなれば、今まで通りの経費を使っていれば、利益を出すことは難しくなるどころか、資金繰りも悪化します

 こういった場合、「当座資産(現金など)」や「内部留保」がない企業は、外部から資金調達できなければ、企業の存続が危うい状態となります
こういった場合、「当座資産(現金など)」や「内部留保」がない企業は、外部から資金調達できなければ、企業の存続が危うい状態となります
 一方、「当座資産」や「内部留保」を充分に蓄えている企業は、少しずつ取り崩しながら、景気が回復するのを待ったり、新しい商品やサービスの開発をすることができるので、少しでも長く企業を存続することができます
一方、「当座資産」や「内部留保」を充分に蓄えている企業は、少しずつ取り崩しながら、景気が回復するのを待ったり、新しい商品やサービスの開発をすることができるので、少しでも長く企業を存続することができます
 注意したいのが、「当座資産」が充分にあっても、「流動負債」が同額、または、当座資産以上にある場合は、資金ショートを起こす可能性があり、企業を存続することができない場合があります(流動比率が100%以下の企業など)
注意したいのが、「当座資産」が充分にあっても、「流動負債」が同額、または、当座資産以上にある場合は、資金ショートを起こす可能性があり、企業を存続することができない場合があります(流動比率が100%以下の企業など)
 【内部留保を高める方法】
【内部留保を高める方法】 1.利益を出すこと
1.利益を出すこと利益が出ない限り、内部留保することはできません。
 2.配当金や役員賞与を少なくする
2.配当金や役員賞与を少なくする配当金や役員賞与は利益の中から支払いすることになりますので、その分内部留保は少なくなります

最近は外国人投資家の比率が高まっているなどの理由により、「株主の利益を重要視して」最終損益が赤字となっていても、「内部留保(利益剰余金)」を取り崩してでも配当するといった企業が増加傾向にあり、賛否両論です

配当金や役員賞与は現金で出ていきますから、当座資産を高めるという見方をすれば、少ないほうが良いです

 3.節税をする
3.節税をする「試験研究費を使った」「教育訓練費を使った」「中小企業が新品の機械や備品や車両を購入した」場合などは、一定の条件はありますが、「法人税を減額する」「圧縮記帳」などといった選択肢もありますので、「社員教育や設備投資の充実を図りながら、税金を少なくし、内部留保を高めること」ができます。
しかし、「法人税が減額となる」からといって、企業にとって不要なものを購入しては、本末転倒です。
 【当座資産を高める方法】
【当座資産を高める方法】 1.配当金や役員賞与を少なくする
1.配当金や役員賞与を少なくする上記の【内部留保を高める方法】を参考にしてください

 2.税金を払う
2.税金を払う税金を払うのはもったいないという認識をしていませんか?
確かに税金の使途によっては、払うのはもったいないかもしれません。
しかし、利益に対して、税金を払うことによって、現金は残ります。(利益で設備投資、借入金の返済をしなかった場合)

損金にできる積立型の生命保険に加入するといった手段などはありますが、税金を払うのが嫌だからといって、企業にとって不要なものを購入すれば、いずれにしても「現金」が出ていきますからお金は残りません

 翌期に「購入」「修理」などを検討しているものであれば、前倒しして経費にするのであればいいと思いますが、100万円の利益がでて税金を払うのが嫌で、100万円分の不必要な経費を使ったとすれば、最終的に現金は残りませんので再度検討すべきです
翌期に「購入」「修理」などを検討しているものであれば、前倒しして経費にするのであればいいと思いますが、100万円の利益がでて税金を払うのが嫌で、100万円分の不必要な経費を使ったとすれば、最終的に現金は残りませんので再度検討すべきです
 また、100万円分の不必要な経費を使うのであれば、利息の付く借入金(有利子負債)を早期に返済し、金利分を節約する方が資金の使い方としては有意義となる場合があります
また、100万円分の不必要な経費を使うのであれば、利息の付く借入金(有利子負債)を早期に返済し、金利分を節約する方が資金の使い方としては有意義となる場合があります
 例えば、100万円の利益で法定実効税率(利益に対する税負担率)が40.87%とすれば「現金が591,300円」残ります
例えば、100万円の利益で法定実効税率(利益に対する税負担率)が40.87%とすれば「現金が591,300円」残ります
********************
法人税など=100万円×40.87%=408,700円
現金・預金=100万円-408,700円=591,300円
*上記の算出式は利益が出ていないときの実効税率で、【法人税率:30%、事業税率:9.6%、住民税率:17.3%】で計算しています。
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引き下げられていますのでお気をつけください。
********************
↓わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください↓
 香川県を活性化させよう
香川県を活性化させようサークルへの参加も宜しくお願い致します。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1958
 ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。
ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。職業に関係なく、是非、ご参加ください。
香川県を盛り上げていきましょう!
香川に縁のある方であれば、誰でも参加OKです。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1959
 顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
お問合せは、プロフィールのホームページから

 また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪
また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪お気軽にお問合せ下さい

以下、用語の簡単な説明です。
********************
 【当座資産】
【当座資産】「現金・預金」「受取手形」「売掛金」「(一時所有の)有価証券」などで、短期間のうち(1年以内)に現金化できる資産のことをいいます。
 【流動負債】
【流動負債】1年以内に支払の期限が到来する債務のことをいいます。
 【流動比率】
【流動比率】「計算式=流動比率(%)=流動資産÷流動負債」で、企業の1年以内の収支倍率(支払能力)を表す数値で、100%以上であれば、1年以内に支払不能になる可能性が低いことを表します。
この数値が低すぎる場合、企業の健全性に問題が生じている可能性がありますが、逆に高すぎる場合も、遊休資産が多いとみなされ、買収の対象になる可能性が高くなります。
 【内部留保】
【内部留保】企業が活動して獲得した利益のうち、「法人税などの税金」「役員賞与」「剰余金による配当」を払った残りで、企業内部へ再投資する目的で蓄積されている部分(利益剰余金)です。
要は、企業の設立から現在までの「利益の累積額」です。
 【法定実効税率】
【法定実効税率】理論上の利益に対する税負担率です。
法人の所得には、条件にもよりますが、基本的には【法人税(国税)30%】【法人住民税(地方税)9.6%】【法人事業税(地方税)17.3%】の税金が課されます。
この3つの税率を単純に加算すると、44.79%となります。
しかし、事業税は支払いをする日を含む事業年度において損金算入(経費)とされるため、結果として節税効果が生じます。
このことを考慮して算出した理論上の利益に対する税負担率を「実効税率」といいます。
算出式は、以下のとおり。
「実効税率=法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率/1+事業税率」
********************
Posted by まこと at 14:07│Comments(0)
│経営・マネジメント