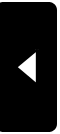「減価償却をしない」「役員報酬の減額」節税できるのはどっち?
2010年10月07日
自分自身が初心を思い出すためのメモ書き
今回は、
「減価償却をしない」「役員報酬の減額」節税できるのはどっち?
「赤字企業「減価償却をしない」と「役員報酬の減額」どちらを優先しますか?」
「赤字企業が現金を残す方法」
についてお話をしようと思います。
 企業を運営していれば、良いときばかりでなく、長引く不況や競合他社の出現などにより、業績が悪化し、赤字決算となる場合もあります
企業を運営していれば、良いときばかりでなく、長引く不況や競合他社の出現などにより、業績が悪化し、赤字決算となる場合もあります
そういった場合に、たとえ赤字決算になったとしても、減価償却費は計上していますか
(わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください )
)
 ときどき、赤字にしたくないために「減価償却」計上しない企業を見かけます
ときどき、赤字にしたくないために「減価償却」計上しない企業を見かけます
赤字が出た事業年度は「減価償却をしない」ことにより、帳簿上は黒字化することが出来ます
しかし、減価償却をせずに利益(黒字)が出たようにしても、見せかけに過ぎません
 最近は銀行などから借入をしている場合や、融資を希望であれば必ず、「減価償却をしているかどうか」を見られると思ってください
最近は銀行などから借入をしている場合や、融資を希望であれば必ず、「減価償却をしているかどうか」を見られると思ってください
どのくらい減価償却費として計上しなければならないのかは「帳簿上」では分からなくても、「申告書上(別表)」はバッチリわかります
 第三者のためでなく、特別な事情がある場合を除き、節税をする意味でも「減価償却を計上して」「役員報酬を下げる」などして調整することをお勧めします
第三者のためでなく、特別な事情がある場合を除き、節税をする意味でも「減価償却を計上して」「役員報酬を下げる」などして調整することをお勧めします
そして、利益が出たときに十分に役員報酬をとるようにして下さい
ただ、役員報酬の増減は、時期や条件が決められておりますので、注意が必要です
 減価償却をせずに最終利益が0円だった場合と、役員報酬を減額して最終利益が0円だった場合は全く違います。
減価償却をせずに最終利益が0円だった場合と、役員報酬を減額して最終利益が0円だった場合は全く違います。
何が違うかというと、
********************
 1.減価償却をせずに、役員報酬を通常通り払って、最終損益0円だった場合
1.減価償却をせずに、役員報酬を通常通り払って、最終損益0円だった場合
 ①減価償却をしていないので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)でなくなります。
①減価償却をしていないので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)でなくなります。
これは、対象の資産を「売却」や「廃棄」などしたときに最終損益に違いがでます。
減価償却をしていなければ、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などに差が出てしまう」ため、多額の「売却損や除却損など」を計上することになり、最終的に正確な損益を把握できなくなることがあります
 ②役員報酬は通常通り支払われていますので「現金・預金」は少なくなっています(支払っておらず、役員借入金にて処理している場合などを除く)
②役員報酬は通常通り支払われていますので「現金・預金」は少なくなっています(支払っておらず、役員借入金にて処理している場合などを除く)
 2.減価償却をして、その分は役員報酬を減額して、最終損益が0円だった場合
2.減価償却をして、その分は役員報酬を減額して、最終損益が0円だった場合
 ①適正な減価償却を計上しているので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)となります。
①適正な減価償却を計上しているので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)となります。
結果、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などの差額が比較的少なくて済む」ため、特別な場合を除き、損益にあまり影響しません
 ②役員報酬を減額するため「現金・預金」に余裕が出来ます
②役員報酬を減額するため「現金・預金」に余裕が出来ます
********************
 上記のように、役員報酬を減額すると、「社長の取り分が減って損する」と思われがちですが、中小企業に限っては、「株主=社長、社長の親族」である場合が多く、企業と社長は「一心同体」と考えてください
上記のように、役員報酬を減額すると、「社長の取り分が減って損する」と思われがちですが、中小企業に限っては、「株主=社長、社長の親族」である場合が多く、企業と社長は「一心同体」と考えてください
 そして、役員報酬を減額するメリットとして、
そして、役員報酬を減額するメリットとして、
 1.社長の役員報酬が減額となった分、社長個人としては減額分だけ我慢しなければなりませんが、会社は減額した分だけ、利益がでます(経費が少なくなるため)
1.社長の役員報酬が減額となった分、社長個人としては減額分だけ我慢しなければなりませんが、会社は減額した分だけ、利益がでます(経費が少なくなるため)
 2.更に、役員報酬が減額となった分「所得税」「住民税」「社会保険料」が少なくてすみます
2.更に、役員報酬が減額となった分「所得税」「住民税」「社会保険料」が少なくてすみます
 一度、社長の役員報酬が100万円減額になったときの「所得税」「住民税」「社会保険料」を試算してみて下さい。
一度、社長の役員報酬が100万円減額になったときの「所得税」「住民税」「社会保険料」を試算してみて下さい。
その分だけ、税務署や社会保険事務所へ払わなくてすみます
 結果、減価償却を計上して、役員報酬を減額した方が、「会社と社長個人」で考えると、余計な現金預金などが出ていかないため、その分内部留保が増加します
結果、減価償却を計上して、役員報酬を減額した方が、「会社と社長個人」で考えると、余計な現金預金などが出ていかないため、その分内部留保が増加します
 しかし、この減価償却ですが、よく、法人化するメリットの一つに挙げられます
しかし、この減価償却ですが、よく、法人化するメリットの一つに挙げられます
というのが、「個人事業者」は強制償却(必ず減価償却をしなければならない)ですが、「法人」であれば任意償却(するかしないかは法人の任意)なのです
そして、青色申告の法人のであれば7年間、繰越欠損金(過去の赤字)を繰り越すことが出来ます。
ですので、繰越欠損金の繰越ができないなどの理由によっては、「減価償却しない」ことにより、有利になる場合もありますので、十分な検討が必要です
( わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください
わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください )
)
 香川県を活性化させよう
香川県を活性化させよう
サークルへの参加も宜しくお願い致します。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1958
 ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。
ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。
職業に関係なく、是非、ご参加ください。
香川県を盛り上げていきましょう!
香川に縁のある方であれば、誰でも参加OKです。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1959
 顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
お問合せは、プロフィールのホームページから
 また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪
また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪
お気軽にお問合せ下さい
 以下、用語の簡単な説明です
以下、用語の簡単な説明です
********************
 【減価償却】
【減価償却】
長い期間にわたって使用できる資産の取得(設備投資)、高額な資産の取得などに要した支出を、その資産が使用できる期間(「耐用年数」法律で定められています)にわたって費用計上することです。
取得した事業年度で一度に経費にしてしまうと、次期以降、極端に言えば、収入だけか発生して、費用が発生しなくなり、「費用収益対応の原則」に反することになります。
 【費用収益対応の原則】
【費用収益対応の原則】
企業の正確な業績(損益)を捉えるために、ある一定の期間(通常は1年決算が多いです)の収益と費用をできる限り正確に把握する必要があります(「期間損益」)。
そこで、「費用収益対応の原則」に基づき企業の期間損益を計算することが求められています。
「火のないところに煙は立たぬ」「蒔かぬ種は生えぬ」といった、ことわざがあるように、「収益のないところには費用はない」「費用、投資がなければ収益は生まない」といったところでしょうか(ちょっと違うか・・・^^;)
********************

今回は、
「減価償却をしない」「役員報酬の減額」節税できるのはどっち?
「赤字企業「減価償却をしない」と「役員報酬の減額」どちらを優先しますか?」
「赤字企業が現金を残す方法」
についてお話をしようと思います。
 企業を運営していれば、良いときばかりでなく、長引く不況や競合他社の出現などにより、業績が悪化し、赤字決算となる場合もあります
企業を運営していれば、良いときばかりでなく、長引く不況や競合他社の出現などにより、業績が悪化し、赤字決算となる場合もあります
そういった場合に、たとえ赤字決算になったとしても、減価償却費は計上していますか

(わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください
 )
) ときどき、赤字にしたくないために「減価償却」計上しない企業を見かけます
ときどき、赤字にしたくないために「減価償却」計上しない企業を見かけます
赤字が出た事業年度は「減価償却をしない」ことにより、帳簿上は黒字化することが出来ます

しかし、減価償却をせずに利益(黒字)が出たようにしても、見せかけに過ぎません

 最近は銀行などから借入をしている場合や、融資を希望であれば必ず、「減価償却をしているかどうか」を見られると思ってください
最近は銀行などから借入をしている場合や、融資を希望であれば必ず、「減価償却をしているかどうか」を見られると思ってください
どのくらい減価償却費として計上しなければならないのかは「帳簿上」では分からなくても、「申告書上(別表)」はバッチリわかります

 第三者のためでなく、特別な事情がある場合を除き、節税をする意味でも「減価償却を計上して」「役員報酬を下げる」などして調整することをお勧めします
第三者のためでなく、特別な事情がある場合を除き、節税をする意味でも「減価償却を計上して」「役員報酬を下げる」などして調整することをお勧めします
そして、利益が出たときに十分に役員報酬をとるようにして下さい

ただ、役員報酬の増減は、時期や条件が決められておりますので、注意が必要です

 減価償却をせずに最終利益が0円だった場合と、役員報酬を減額して最終利益が0円だった場合は全く違います。
減価償却をせずに最終利益が0円だった場合と、役員報酬を減額して最終利益が0円だった場合は全く違います。何が違うかというと、
********************
 1.減価償却をせずに、役員報酬を通常通り払って、最終損益0円だった場合
1.減価償却をせずに、役員報酬を通常通り払って、最終損益0円だった場合 ①減価償却をしていないので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)でなくなります。
①減価償却をしていないので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)でなくなります。これは、対象の資産を「売却」や「廃棄」などしたときに最終損益に違いがでます。
減価償却をしていなければ、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などに差が出てしまう」ため、多額の「売却損や除却損など」を計上することになり、最終的に正確な損益を把握できなくなることがあります
 ②役員報酬は通常通り支払われていますので「現金・預金」は少なくなっています(支払っておらず、役員借入金にて処理している場合などを除く)
②役員報酬は通常通り支払われていますので「現金・預金」は少なくなっています(支払っておらず、役員借入金にて処理している場合などを除く)
 2.減価償却をして、その分は役員報酬を減額して、最終損益が0円だった場合
2.減価償却をして、その分は役員報酬を減額して、最終損益が0円だった場合 ①適正な減価償却を計上しているので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)となります。
①適正な減価償却を計上しているので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)となります。結果、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などの差額が比較的少なくて済む」ため、特別な場合を除き、損益にあまり影響しません
 ②役員報酬を減額するため「現金・預金」に余裕が出来ます
②役員報酬を減額するため「現金・預金」に余裕が出来ます
********************
 上記のように、役員報酬を減額すると、「社長の取り分が減って損する」と思われがちですが、中小企業に限っては、「株主=社長、社長の親族」である場合が多く、企業と社長は「一心同体」と考えてください
上記のように、役員報酬を減額すると、「社長の取り分が減って損する」と思われがちですが、中小企業に限っては、「株主=社長、社長の親族」である場合が多く、企業と社長は「一心同体」と考えてください
 そして、役員報酬を減額するメリットとして、
そして、役員報酬を減額するメリットとして、 1.社長の役員報酬が減額となった分、社長個人としては減額分だけ我慢しなければなりませんが、会社は減額した分だけ、利益がでます(経費が少なくなるため)
1.社長の役員報酬が減額となった分、社長個人としては減額分だけ我慢しなければなりませんが、会社は減額した分だけ、利益がでます(経費が少なくなるため)
 2.更に、役員報酬が減額となった分「所得税」「住民税」「社会保険料」が少なくてすみます
2.更に、役員報酬が減額となった分「所得税」「住民税」「社会保険料」が少なくてすみます
 一度、社長の役員報酬が100万円減額になったときの「所得税」「住民税」「社会保険料」を試算してみて下さい。
一度、社長の役員報酬が100万円減額になったときの「所得税」「住民税」「社会保険料」を試算してみて下さい。その分だけ、税務署や社会保険事務所へ払わなくてすみます

 結果、減価償却を計上して、役員報酬を減額した方が、「会社と社長個人」で考えると、余計な現金預金などが出ていかないため、その分内部留保が増加します
結果、減価償却を計上して、役員報酬を減額した方が、「会社と社長個人」で考えると、余計な現金預金などが出ていかないため、その分内部留保が増加します
 しかし、この減価償却ですが、よく、法人化するメリットの一つに挙げられます
しかし、この減価償却ですが、よく、法人化するメリットの一つに挙げられますというのが、「個人事業者」は強制償却(必ず減価償却をしなければならない)ですが、「法人」であれば任意償却(するかしないかは法人の任意)なのです

そして、青色申告の法人のであれば7年間、繰越欠損金(過去の赤字)を繰り越すことが出来ます。
ですので、繰越欠損金の繰越ができないなどの理由によっては、「減価償却しない」ことにより、有利になる場合もありますので、十分な検討が必要です

(
 わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください
わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください )
) 香川県を活性化させよう
香川県を活性化させようサークルへの参加も宜しくお願い致します。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1958
 ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。
ビジネスや趣味で様々な方の交流の場になればと思い作成しました。職業に関係なく、是非、ご参加ください。
香川県を盛り上げていきましょう!
香川に縁のある方であれば、誰でも参加OKです。
http://saakuru.atja.jp/commu_detail.php?sid=ashita-sanuki.jp&commu_id=1959
 顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
顧客満足度の高い広告宣伝を完全成功報酬でお受け致します
お問合せは、プロフィールのホームページから

 また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪
また、売る仕組み(セール方法)ではなく、売れる仕組み(マーケティング)のツールの提案・提供やマーケティングを活かしたコンサルタント業務を手掛けております♪お気軽にお問合せ下さい

 以下、用語の簡単な説明です
以下、用語の簡単な説明です
********************
 【減価償却】
【減価償却】長い期間にわたって使用できる資産の取得(設備投資)、高額な資産の取得などに要した支出を、その資産が使用できる期間(「耐用年数」法律で定められています)にわたって費用計上することです。
取得した事業年度で一度に経費にしてしまうと、次期以降、極端に言えば、収入だけか発生して、費用が発生しなくなり、「費用収益対応の原則」に反することになります。
 【費用収益対応の原則】
【費用収益対応の原則】企業の正確な業績(損益)を捉えるために、ある一定の期間(通常は1年決算が多いです)の収益と費用をできる限り正確に把握する必要があります(「期間損益」)。
そこで、「費用収益対応の原則」に基づき企業の期間損益を計算することが求められています。
「火のないところに煙は立たぬ」「蒔かぬ種は生えぬ」といった、ことわざがあるように、「収益のないところには費用はない」「費用、投資がなければ収益は生まない」といったところでしょうか(ちょっと違うか・・・^^;)

********************
Posted by まこと at 10:32│Comments(0)
│経営・マネジメント